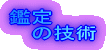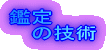━建窯についての大事な話し━
中国福建省のかの有名な建窯、
あの禾目天目や曜変天目茶碗(国宝)を焼いた古代窯のことです。
建窯が天目茶碗を」専門に焼いたといえども
じつは、杯等の酒器も焼成していた事はあまり知られていません。
先日、建窯の遺跡をよく識っている友人に会い現地の窯址の話しをした折のこと。
私の質問は、茶碗や杯の見込みに厚く溜まった斜めの釉だまりの事に及んだ。
(建窯の茶碗や杯には斜めの釉だまりが多い)
友人いわく、発掘調査された宋代の登り窯(階級窯)の一本の長さは約80〜120mで、
周辺の地域に約300本ほどあるとのこと。 (階級窯の傾斜角度は約15度前後)
また窯は一度の焼成で1.000個前後の品を焼いたようだ。
焼成室の床面が階段状の水平面と思っていた登り窯は、やや傾斜面を残した平面で、
茶碗や杯を入れたサヤはこれまた垂直を得ない4〜5つ重ねの状態であったと説明された。
(燃焼室からの火力風のためわざわざ傾斜に置いたとの説もある)
要するに現代作家の窯を想像すべきでなく、商品の量の多さと窯の長さを考慮すると
中国の古代窯の往時の活動の実態は大きく日本の古窯と異なるようです
(しかし、以上の話は宮中への貢品や、高級品の作調とは異なるかもしれません)
 |
 |
柿釉笠形杯
建窯 南宋
口径 9.5cm
高さ 4.0cm
|
|
|